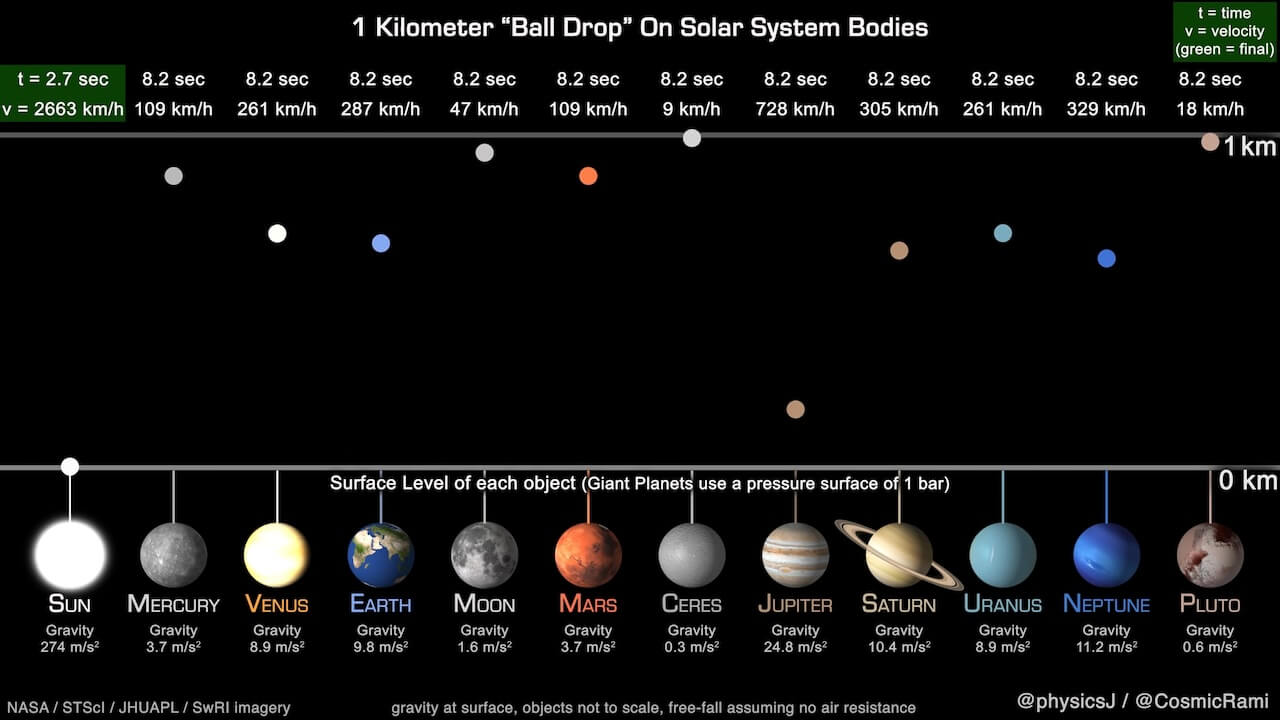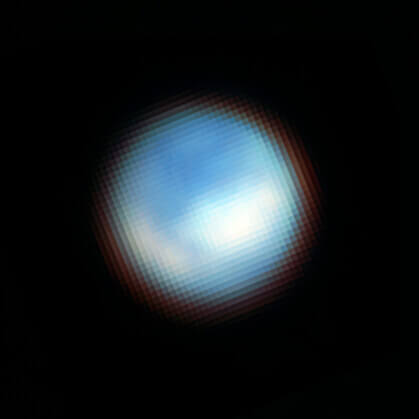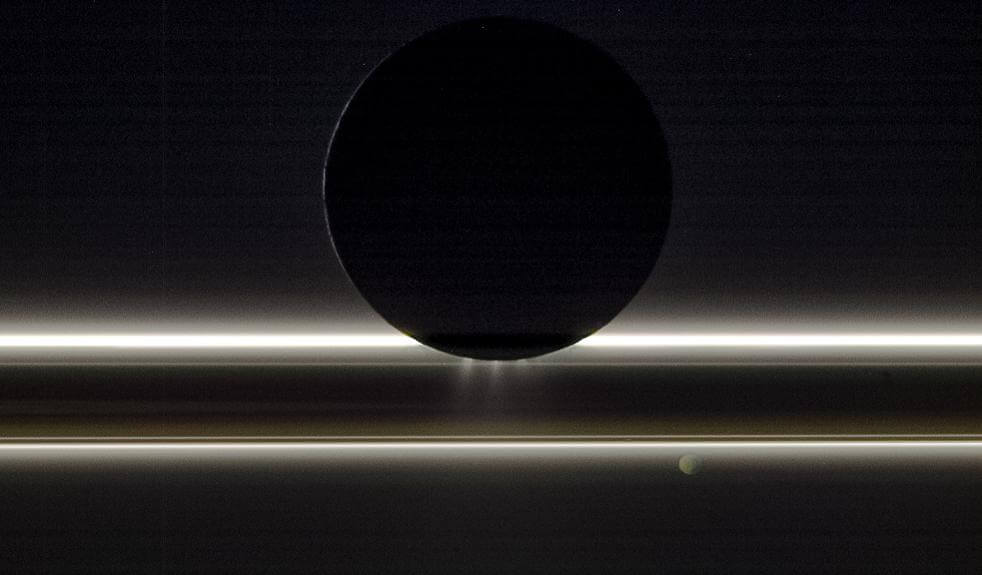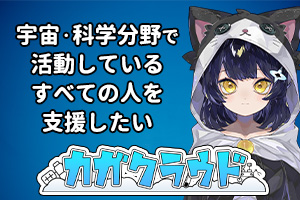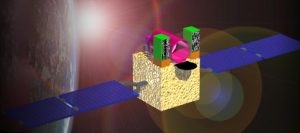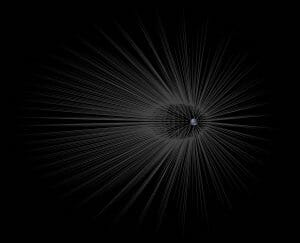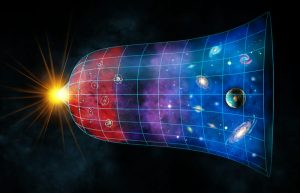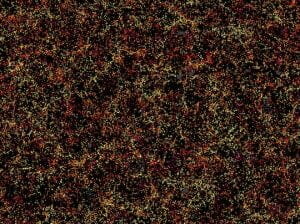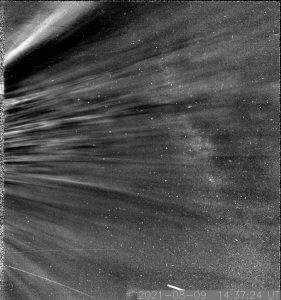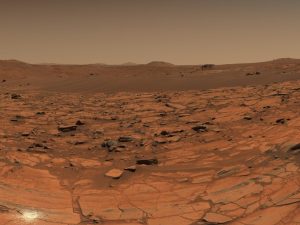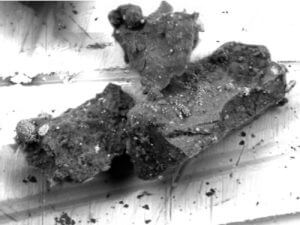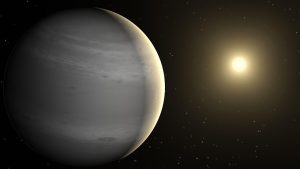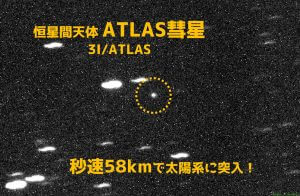こちらは「きょしちょう座(巨嘴鳥座)」の方向約20万光年先の散開星団「NGC 346」とその周辺の様子です。画像の縦方向に湾曲しながら伸びるピンク色をした暗い雲の連なりは、どこかタツノオトシゴを思わせるシルエットをしています。その傍らでは、いくつもの星団の星々が青色の輝きを力強く放っています。

若き星団と星雲が織りなすアートのような宇宙の景色
この画像は「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)」で取得した赤外線・可視光線・紫外線の観測データを使って作成されました。NGC 346は天の川銀河の衛星銀河(伴銀河)のひとつである「小マゼラン雲(Small Magellanic Cloud: SMC)」にあります。
ESA=ヨーロッパ宇宙機関(欧州宇宙機関)によると、この星団には新たに生まれた恒星が2500個以上存在しています。11年間隔で取得された2組のデータセットを分析した結果、NGC 346の星々は星団の中心に向かってらせんを描くように動いていることがわかりました。星々の動きは星団の外側からやってきたガスの流れによって引き起こされたもので、この流れが中心部における星形成を促進しているのだといいます。
また、NGC 346の若い星々は強力な光(電磁波)や激しい恒星風を発することで、自らを生み出したガスと塵(ダスト)の雲を周囲から吹き払っています。その結果として、星団の周囲には「N66」と呼ばれる輝線星雲が形作られました。
輝線星雲は若い大質量星から放射された紫外線によって電離した水素ガスが光を放っている星雲で、HII(エイチツー)領域とも呼ばれています。HII領域が輝く期間は、星雲を照らす大質量星が輝くのと同程度の数百万年ほど。若い星々が集まった星団と同じように、長い宇宙の歴史ではほんのひと時だけ輝く儚い存在なのです。
冒頭の画像は2025年4月のハッブル宇宙望遠鏡打ち上げ35周年記念の一環として作成されたもので、ESAから2025年4月4日付で公開されています。
文/ソラノサキ 編集/sorae編集部
関連記事
- 幅広な渦巻腕が印象的 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“おとめ座”の渦巻銀河「NGC 4941」(2025年3月31日)
- 20万光年先の宝石箱 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した星団「NGC 346」(2025年3月18日)
参考文献・出典
- ESA - Hubble spots stellar sculptors at work in a nearby galaxy